音楽でいう「学習効果」とは、何度も経験するうちに耳と脳が「こういう音はこう聞こえるんだ」と覚えていくことです。
たとえば——
- 音が右から来るときの耳の感じ方(時間のずれ・大きさの違い)
- 上から聞こえるときのちょっとした音色の変化
- 部屋の響き方で近い・遠いを感じること
こうした“音の手掛かり”を、繰り返し聴いて体験することで、だんだん正しく判断できるようになります。
つまり学習効果は、「耳が経験を通して成長する仕組み」なのです。
用語の最短定義
- 垂直定位:音が上か下かを判断すること。
- 学習効果:反復経験により、脳が“手掛かり”と答えを結び付け、判断の精度と速度が向上すること。
- 耳介フィルタ(HRTF由来):耳介・頭部・胴体で生じる個人固有の周波数バランス(スペクトル差)。
- 微回転(head-tilt / head-turn):5〜10°程度ゆっくり首を回し、比較材料(差分)を作る操作。
HRTFとは?
頭部伝達関数(とうぶでんたつかんすう、Head-Related Transfer Function, HRTF)のこと。耳殻、人頭および肩までふくめた周辺物によって生じる音の変化を伝達関数として表現したものである。
要点
- 主張:上下定位は学習効果で安定する。
- 根拠:水平は ITD/ILD(時間差・レベル差)の寄与が大きいが、垂直は耳介由来のスペクトル差が主手掛かり。この手掛かりは個体差が大きいため、脳が自分固有のHRTFを経験で学習する必要がある。
- 補助手段:微回転により耳介フィルタの当たり方が微妙に変わり、差分比較が生まれる → 脳が対応づけを強化 → 上下の定位が安定。
ミニ練習(30〜60秒)
スマホやPCからYouTubeなどでピンクノイズ/クリックなど高域を含む短音を再生。推奨は有線オーバーイヤー or 小型スピーカーをつかい、正面固定のまま首を5–10°だけゆっくり回す/傾ける。
ノイズの明るさや輪郭の微変化を1行で言語化。翌日、同条件で同じ言語化が再現すれば定位が安定してきているサイン。
図解(簡易)
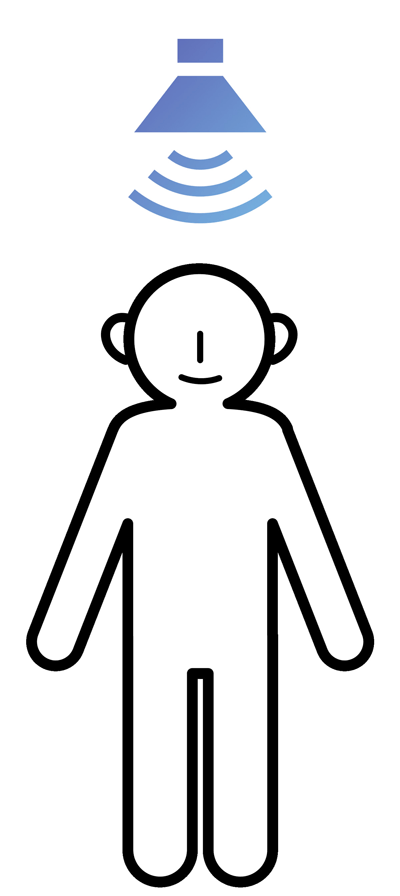
首の微回転で生じた音色差(スペクトル差)を比較し、経験で上下の判断が安定する(=学習効果)。
QMS|2025年問題ステップⅠ問題12
本回のQMSは【2025年 ステップⅠ 第12問】をアレンジ。定番テーマの再出題が多く、過去問学習が最短ルートです。
対話講義
タカミックス
上下の定位って、どうすれば判断が安定しますか?沢山の音楽を聞けば良いのですか?
サウンド先生
学習効果だよ。ただしタカミックスくんの言うような“量”じゃない。正面からピンクノイズやクリックなどを鳴らし、5〜10°だけゆっくり首を回して(または軽く傾けて)微回転を作り、その差分を比較する。
さらに、ラベル付き素材(上/正面/やや下が分かる提示)を使い、同じ環境を保って反復する。
タカミックス
ラベル付き素材?
サウンド先生
あらかじめ「上」「正面」「下」と方向をアナウンスしてくれるバイノーラル(両耳録音)のデモがある。そういう“正解が分かっている素材”を使うんだ。最初から正解を知った状態で聴くと、脳が「音色の違いと方向」を結び付けやすい。
タカミックス
実践のコツは?
サウンド先生
ピンクノイズやクリックみたいに高域が出る短い音を題材にすると変化をつかみやすい。商用曲は水平の情報が中心だから、上下の練習には不向きだね。
それから注意点がある。
最近のスマホ+イヤホン環境だと、上下の違いはほとんど感じ取れないんだ。なぜなら、最近のイヤホンにはノイズキャンセリング機能がついていて、これは耳介のクセ(HRTF)をDSP(デジタル信号処理)や密閉構造で均してしまうからなんだよ。
タカミックス
じゃあどうすればいいんですか?
サウンド先生
有線のオーバーイヤー型ヘッドホン(できれば開放型)か近距離でスピーカーを鳴らすのがベスト。どうしてもイヤホンしかないなら、空間オーディオやノイズキャンセリング機能をオフにして、音量と姿勢を固定して試すと少しは分かりやすくなるよ。
タカミックス
まとめると?
サウンド先生
上下はHRTF由来の“音色の手掛かり”。微回転+反復+言語化で脳内に対応づけができ、定位が安定する。
他の選択肢が×の理由
- 近接効果:単一指向性マイクで近距離時に低域がブーストされる現象。定位学習と無関係。
- コンター効果:等ラウドネス関連の音量による帯域の聞こえ方の変化。上下定位の説明ではない。
- コーラス効果:微小ピッチ/時間変調の厚み系エフェクト。定位学習と無関係。
この授業のまとめ
- 垂直定位の主手掛かりは耳介由来のスペクトル差。
- 学習効果(経験・記憶・条件づけ+微回転による差分比較)で定位が安定する。
過去問出題年
検証中(今後追記予定)



